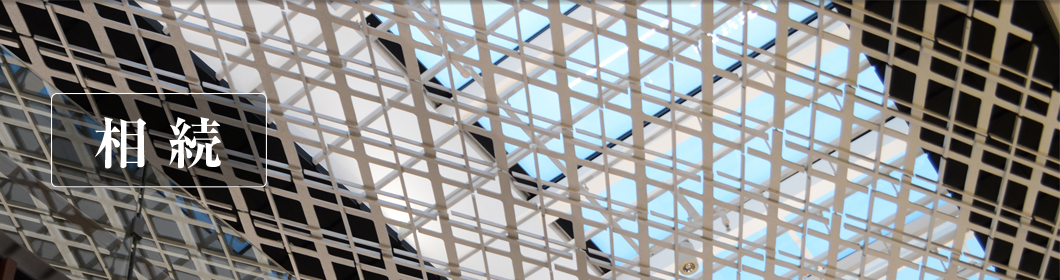
遺言
遺言の役割
近年、遺産分割調停・審判事件は増加傾向にあり(下記図①参照)、相続人間で遺産分割協議がまとまらず相続財産を巡って裁判所を巻き込んだ紛争に発展するケースが増えてきていることがわかります。そして、遺産分割を巡る紛争は、相続財産の多寡に関わらず発生しており(下記図②参照)、遺産分割協議中の何気ない言動によって相続人間に感情的な対立が生じ、紛争に発展してしまうケースも決して珍しいことではありません。
このような『争族』防止のために重要な役割を果たすのが遺言の制度です。
「遺言」とは、自己の最終意思(特に相続財産との関係)を後世に残すものです。遺言が存在すれば、紛争の温床となる遺産分割手続を経ることなく相続財産を各相続人に承継させることができますので、遺言には、遺産分割を通じた相続人間の争いを未然に防ぐという重要な役割があるといえます。
遺産分割調停・審判事件数の増加とともに、公正証書遺言作成件数、遺言書の検認件数も増加傾向にあり(下記図①参照)、遺言の重要性につき、国民の認識が高まっていることが窺えます。


遺言の種類と作成方法
遺言には、大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言の2種類があり、普通方式の遺言は、更に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられます。この内、実務上頻繁に利用されているのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
1. 自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、遺言者自身が遺言の全文、日付及び氏名を手書きし、押印して作成する遺言のことをいいます。ただし、平成30年相続法改正により、財産目録(遺産目録)に限っては手書きで作成する必要がなくなりました(施行日:平成31年1月13日)。
自筆証書遺言は、遺言者によって適当な場所で保管され、遺言者の死後は、家庭裁判所による検認手続を経て執行する必要があります。もっとも、平成30年に法務局における遺言書の保管等に関する法律が制定されたことで、自筆証書遺言を法務局において保管する制度(自筆証書遺言保管制度)が新たに設けられましたので(施行日:令和2年7月10日)、この制度を利用した場合には例外的に検認手続を経る必要はありません。
自筆証書遺言は、誰にも知られず、好きな時に、かつ特段費用をかけることなく作成できるというメリットがありますが、他方で、その方式は法律上厳格に定められており、仮に方式違反が存在すると遺言が無効となってしまうリスクがあるという重大なデメリットがあります。
また、誰の関与もなく作成されるため、遺言者が遺言作成時において高齢であって、認知症の疑いがある場合などには、遺言者の死後に遺言者の遺言能力(15歳以上の者であって、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足りる意思能力)の有無を巡って相続人間で争いが生じるおそれがあります。
更には、遺言の保管態様によっては、遺言作成後に破棄・改ざん・隠匿されてしまうリスクもあり、この疑念が「争族」のきっかけとなることもあります。
折角作成した遺言の効力につき相続人間で争いを生じさせないために、また後世に自己の最終意思を確実に伝えるためにも、遺言を作成する場合は、原則として後述する公正証書遺言を利用するべきです。また、仮に自筆証書遺言を作成する場合であっても、法律の専門家である弁護士に依頼し、自筆証書遺言の文案の作成や内容・形式の確認を経ることが肝要です。
2. 公正証書遺言
「公正証書遺言」とは、証人2名の立ち会いの下、法律専門家である公証人が関与して公正証書として作成される遺言のことをいいます。
第三者である公証人が被相続人の意思確認を行った上で作成する遺言ですので、「被相続人の真意に基づくものではない」、「遺言能力がない」などとして、その効力を相続人が争う余地の少ない遺言といえます。
また、専門家の公証人が主導して作成しますので、被相続人が自ら方式違反について特に注意を払う必要がなく安心して作成できるという点もメリットとして挙げられます。
他方で証人2名の立ち会いを要するため、自筆証書遺言とは異なり、遺言者以外の者に遺言の内容が知られてしまうというデメリットもあります。
公正証書遺言を作成する場合にも、遺言書作成の法的ポイントについてアドバイスできる弁護士に依頼することをお勧めします。また、併せて弁護士に証人となることを依頼することで、遺言内容を秘密にしておくことができます。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットについては、以下の表をご参照下さい。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 |
|
|
| 公正証書遺言 |
|
|
遺言事項
遺言に記載することで法的効力を持つ事項を「法定遺言事項」といいます。
法定遺言事項は、一般的に知られている相続分や遺産分割方法の指定、遺贈等の財産に関する事項に限られません。例えば身分に関する事項として、推定相続人の廃除、子の認知、未成年後見人の指定をすることができ、遺言執行に関する事項として、遺言執行者の指定を行うこともできます。
また、法的効力は生じませんが、遺言には、なぜそのような内容の遺言をしたのか、自らの想いを相続人に伝えるため、「付言事項」を記載することもできます。付言事項は、相続人間の争いを未然に防ぐ事実上の効果があるほか、場合によっては法定遺言事項の解釈に影響を与えることもありますので、遺言には、相続人の感情面にも配慮した適切な付言事項を記載することが好ましいといえます。
遺言執行者
「遺言執行者」とは、遺言の内容を法的に実現する者をいい、前述したとおり遺言によって定めることができます。遺言執行の対象は、法定遺言事項に限られています。
遺言執行者は、未成年者又は破産者以外であって、意思能力がある者であれば誰でも就職することができ、実務上は遺言書において推定相続人1名を遺言執行者と定める場合が多く見受けられます。
もっとも、遺言執行者を相続人と定めた場合には、財産に関する事項の執行手続の実施を通じて、他の共同相続人との間でトラブルに発展するケースが多く、また身分関係に関する事項について遺言が行われているときには、認知の手続など各種法的手続が必要となりますが、相続人自らこれらの手続を行うことは困難です。
そのため、遺言執行者には、各種手続に精通した公平な第三者である弁護士を指定しておくことが適切です。
遺言書作成の法的ポイント
紛争の未然防止という遺言の役割を最大限発揮させるために、遺言には全ての財産を漏れなく記載することが重要であり、また各相続人に如何なる財産を相続させるかを決定するに当たっては、後述する遺留分との関係を無視することはできません。
仮に推定相続人の遺留分を侵害する内容の遺言を作成してしまうと、被相続人の死後に遺産分割手続から遺留分侵害額(減殺)請求調停・訴訟へと場所を変えて紛争が発生することになりかねません。
また、遺言者が会社経営者である場合には、円滑な事業承継を図れるようにするために、承継者に株式その他の事業用資産が承継されるような内容の遺言をすることが必要不可欠です。
将来如何なる類型・態様の紛争が想定されるかは、遺言者や相続人の属性、相続人間の関係性、相続財産の内容など、事案に応じて様々ですので、遺言書作成にあたっては、具体的事案に応じた有効かつ適切な法的アドバイスが可能な弁護士に依頼すべきです。

